Cases
株式会社アダストリア様

株式会社アダストリア様
1953年創業のファッションSPA(製造小売業)カンパニー。
グローバルワーク、ニコアンド、ローリーズファームをはじめとする
ブランドを多数展開しています。
※部署名・役職・内容は取材当時(2024年9月)のものです。
お話をうかがった人
DX本部 副本部長
梅田 和義さん
日本気象協会の「気象予測サービス」の活用状況について教えてください。

これまでアダストリアでは、日本気象協会から提供される「6カ月先予測」や「15週先予測」などのデータを活用し、商品の生産や販売計画に役立ててきました。
二十四節気を基にした気象データを参考にして、例えば、気温が急に下がる時期にコートを前倒しで販売したり、暑い日が続くと予想されるときにTシャツなどの軽衣料を増産したり、消費者の需要に合わせて生産体制を整えることができました。
しかし、近年の異常気象や気温の不安定さから、「毎年同じようにはいかない」という課題が顕著になってきました。
ファッションロス削減に向けた取り組みと課題

アダストリアでは、サステナビリティにおける重点テーマの一つに「環境を守る」を掲げており、ファッションロスのない社会の実現に向けて様々な取り組みを行っています。
ファッションロスとは、まだ着られるにも関わらず、衣類がリユース・リサイクルされることなく、単純焼却・単純埋め立て(廃棄)されてしまう問題を指します。ファッションロスは、過剰消費や焼却廃棄などによるCO₂排出量の増加にもつながり、ファッション業界にとって解決すべき重要課題の一つです。
当社では、「衣料品在庫の焼却処分ゼロ」を具体的目標に掲げ、緻密な仕入れ計画と在庫管理、サーキュラー事業を通じた残在庫活用など、「燃やさない、捨てない」ための様々な取り組みにより、この目標を継続して達成しています。
このテーマと気象データの活用は、深く結びつくのではないでしょうか。過剰な生産や廃棄を減らし、持続可能なビジネスモデルを実現することができると思います。
今までも日本気象協会から提供される6か月予報を活用し、生産計画や販売計画に活用していました。ただ、6か月先までだと生産量の決定時期に届かない課題があり、より長期の予報を精度高く提供してもらいたいと考えていました。
そうした状況下で、日本気象協会から最初に2年先までの長期予測の開発の話を聞いた時には、是非当社としても協力したい旨をお伝えしました。
どういったレポートがあればアパレルの現場で利用しやすいかなど、いろいろとアドバイスさせていただくことや、実際に2年先長期気象予測のサービスを導入した際に、どういった効果が見込めるかなどを検証するために、アダストリアの売上データを提供することなどで協力しました。
実際に日本気象協会のシミュレーションでは、2年先長期気象予測を活用することで、ファッションロスを最大14%削減できる可能性が示されています。この数字は十分に大きいと感じました。この予測データを活用すれば、在庫の管理がより的確に行えるため、無駄な商品生産を抑制することができると考えています。
日本気象協会の2年先長期気象予測は、まさに当社のファッションロスを削減して環境を守るという理念の実現にも大いに役立つと考えます。今後もこの理念に沿った取り組みを進めていく方針です。
気象予測サービスをもっと活用し、お客様のファッション購入体験をより良いものに

当社の商品の売れ行きにも大きな影響を与える気象ですが、生産量の最適化といったビジネス的なロスの削減だけでなく、販売の現場など、もっとあらゆる場面に活用して、お客様により良い体験を与えるお店作り、ブランド作りに活かしていきたいと考えています。
アダストリアは、当社のビジネスを通じて、お客様に幸せになっていただきたいと考えています。
いい服を購入できると、嬉しさを感じていただけると思います。
当社は、お客様が欲しいと思う服を欲しいタイミングで提供し、お客様により良い購入体験をしていただくことを目指しています。
そのため、気象データを参考に、いつどのようなアイテムが求められるかを先回りして準備したいと思っています。
お客様に「このお店に行けばいつも自分が欲しい服がある」と感じてもらえることで、お客様のファッション購入体験がより良いものとなり、ブランドやお店の価値向上にもつながると考えます。
そのためには売り場づくりだけでなく、スタッフへのレクチャーも重要になります。
気象予測をどのように活用するか、現場のスタッフが正確に理解していないと、せっかくのデータを活かしきれません。ですので、データを基にした販売戦略や在庫管理の手法について、スタッフに理解を深めてもらうための資料作りなどを日本気象協会と一緒に考えていきたいです。
今後、どんなサービスがあればいいと思いますか?

現時点では、日本気象協会の「2年先長期気象予測」の当社での活用はまだ始まったばかりで、今後の成果を予測しながら試行錯誤を繰り返しています。
まだ手探りの状態ではありますが、この新しいサービスがもたらす結果に期待を寄せています。
今後の展望としては、気象データをもとに、さらに多様な「指数」を活用できるようなサービスがあれば良いと考えています。
たとえば、気温以外の気象要素も加味した予測を行うことで、より詳細なMD(マーチャンダイジング)の立案につながるかもしれません。
また、こうしたデータを具体的にどのように解釈し、実際のビジネス戦略に組み込むかについての指針も提供してもらえれば、企業にとって大きな助けとなるでしょう。
データを活用して、効率的に商品を企画し、生産し、販売できることを期待しています。
日本気象協会から提供されるさまざまな気象予測は、アダストリアの商品の企画段階から販売戦略に至るまで、幅広い場面で活用される可能性があります。
今後も、このサービスを通じて、より正確な予測データを活用し、消費者のニーズに応えながら、持続可能なビジネスモデルを構築していきたいと考えています。

F-LINE株式会社様
F-LINE出資メーカーをはじめとする荷主の食品・飲料商品の物流。
常温・冷凍・冷蔵などさまざまな温度帯や商品ごとの物流特性、さらに環境負荷低減にも考慮した効率的な物流ネットワークを構築しています。
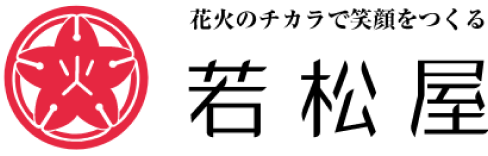
株式会社若松屋様
1937(昭和12)年創業。花火大会の尺玉から身近なおもちゃ花火まで幅広く製造販売。
花火ができる場所検索アプリ「Hanabi-Navi」のリリース、花火の遊び方のマナー向上のためのワークショップを開催するなど活動の幅を広げています。

株式会社AgriweB様
「農業の価値を広げ、社会の未来を実らす、ビジネス共創型マルチサイドプラットフォーム」をコンセプトに、農業のニーズと社会のニーズをつなぐことを目的とした各種サービスをポータルサイト「AgriweB」にて提供しています。

株式会社ジェイアール東日本企画様
1988年に設立されたJR東日本グループの総合広告会社であり、同時に交通広告を有する媒体社の側面も持つ企業。駅や電車などの公共交通機関を活用できる強みを生かし、既成概念にとらわれないクロスメディア提案やコンテンツ企画を次々と実現しています。企業ミッションは「好奇心あふれる日常を」。心躍る出会いや体験を通して、想像以上の日常を創り出すことを目指しています。
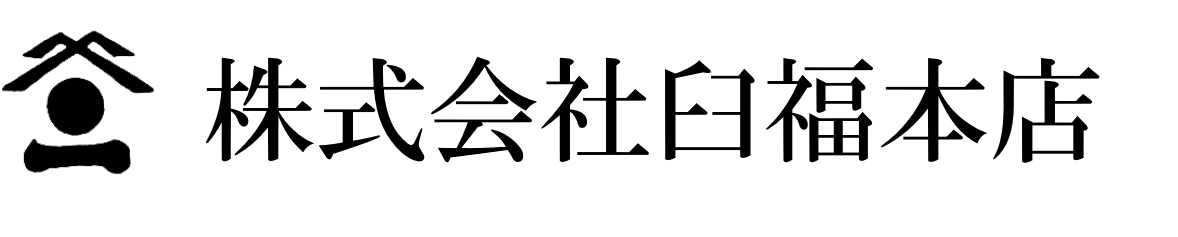
株式会社臼福本店様
明治15年に魚問屋として創業した、約130年の歴史を持つ漁業会社。三代目から本格的に漁業に参画、四代目から遠洋まぐろ延縄漁船一本に切り替え、現在で五代目。震災を契機に、より多くの業界の方々とのつながり手を携えることが、被災地の復興だけでなく漁業の復興、日本全体の復興につながると考え、そのカギが、気仙沼そして東北の第一次産業の復興にあると、社員一同信じています。
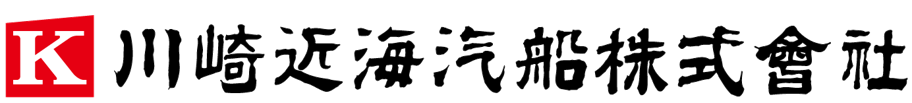
川崎近海汽船株式會社様
1966年に内航海運企業として創業後、近海、フェリー事業、近年ではオフショア支援船部門へと業容を広げ、「海上輸送のベストパートナーとしてお客様のニーズに応え、人に優しい豊かな社会実現に向け貢献」を理念に海陸役職員一丸となり、海上輸送と社会資本インフラを支えています。

川近シップマネージメント株式会社様
川崎近海汽船(株)の100%出資会社。同社グループが保有する内航貨物船の保船管理及び配乗が主たる業務。1万トン級のRO/RO船他、石炭専用船などの船舶管理に携わり、他社に先駆けて安全管理システム(ISMコード)を導入し、安全かつ運航性能効率化を目指しています。
